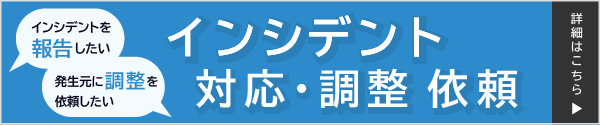2018年7月10日
サイバーセキュリティ対策活動への協力者に感謝状贈呈
一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター
2018年7月、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)は、サイバーセキュリティ対策活動に特に顕著なご貢献をいただいた方に感謝の意を表して記念の盾とともに感謝状を贈呈しました。
昨今、WannaCrypt(WannaCry)をはじめとしたマルウエアによる被害が一般のニュースでも報じられているように、国内外に影響を及ぼすさまざまなサイバー攻撃による被害は後を絶ちません。また、その攻撃手法は日々姿かたちを変え、悪質化、巧妙化の一途をたどっています。
JPCERT/CCは、こうした国内のサイバー攻撃の被害を低減するために、インシデントへの対応支援活動、インシデントを未然に防ぐための早期警戒活動、マルウエア分析、ソフトウエア製品等の脆弱性に関する調整活動などを行っています。これらの活動を円滑かつ効果的に進めるためには、皆様からの情報提供やさまざまなご協力が欠かせません。
JPCERT/CCでは、サイバーセキュリティ対策活動に対する皆様からの御好意と御力添えに深く思いをいたし、第5回目となる2018年度は次の方に感謝状と記念の盾を贈呈致しました。
(五十音順)
フィッシング対策協議会 内田 勝也 様 野々下 幸治 様
 (左:JPCERT/CC 歌代、中央:情報セキュリティ大学院大学 内田様、右:トレンドマイクロ株式会社 野々下様)
(左:JPCERT/CC 歌代、中央:情報セキュリティ大学院大学 内田様、右:トレンドマイクロ株式会社 野々下様)
|
内田氏ならびに野々下氏は、フィッシング対策協議会(※)の設立の翌年2006年から現在まで、同協議会のフィッシング対策を検討するワーキンググループの主査、副主査としてご活動されています。2006年にワーキンググループにてフィッシング対策の技術動向や制度等についての調査を実施し、その結果をまとめた「フィッシング対策における技術・制度調査報告書」は、現在も毎年改訂を行っている「フィッシング対策ガイドライン」の礎となりました。「フィッシング対策ガイドライン」はフィッシング対策の指針として、金融機関やEC業界などさまざまな組織で有効活用されています。また、2013年からは、一般消費者に向けた「インターネットバンキングの不正送金被害にあわないためのガイドライン」の策定に中心になって取り組まれるなど、長年にわたって日本国内全体のフィッシング被害の低減に貢献されています。 (※)フィッシング対策協議会: 日本国内におけるフィッシング詐欺被害の抑制を目的として2005年4月に発足。フィッシング詐欺の事例や対策技術に関する情報の収集、および緊急情報や各種ガイドライン「フィッシング対策ガイドライン」や「利用者向けフィッシング詐欺対策ガイドライン」、「フィッシングレポート」を毎年作成・公開し、フィッシング対策の普及啓発活動に取り組んでいる。 内田 勝也 氏(情報セキュリティ大学院大学 名誉教授) 2007年から現在まで、フィッシング対策協議会のフィッシング被害にあわないための対策等を検討するワーキンググループの主査を務めている 野々下 幸治 氏(トレンドマイクロ株式会社 セキュリティエキスパート本部 エンタープライズCSM部 シニアプリンシパルカスタマーサービスマネージャー) 2006年から現在まで、フィッシング対策協議会のフィッシング被害にあわないための対策等を検討するワーキンググループの主査、および副主査を務めている |
株式会社アイ・オー・データ機器 島田 康晴 様
 (左:JPCERT/CC 歌代、右:株式会社アイ・オー・データ機器 島田様)
(左:JPCERT/CC 歌代、右:株式会社アイ・オー・データ機器 島田様)
|
株式会社アイ・オー・データ機器は、国内における一般消費者向けのデジタル家電周辺機器ベンダーとして自社製品のセキュリティ向上に積極的に取り組み、自ら発見した脆弱性を届けて公表し、広くユーザに周知するなど被害の拡大を防ぐ活動を行っています。 島田氏は、株式会社アイ・オー・データ機器の POC(Point of Contact: 組織の窓口)として、2016年ころから問題となっていたIoT機器を対象にしたボットネットに関して届け出をいただくなどJPCERT/CCの活動に協力いただくとともに、自社製品の脆弱性への取り組みについて対外的に発表を行っています。 自社製品の脆弱性の開示は製品販売上、不利に働く可能性もあるため、消極的な開発者も多い中、積極的に情報開示を行うなど、国内の業界全体のレベル向上に貢献されています。 |
JPCERT/CCからの感謝状の贈呈について:
国内においてサイバーセキュリティインシデントの被害の低減に大きく貢献した方に感謝の意を表することを目的に「JPCERT/CC感謝状制度」を2014年4月に制定いたしました。これに基づいて、顕著なご貢献をいただいた方々に、年1回JPCERT/CCより感謝状を贈呈させていただくものです。
JPCERT/CC 感謝状